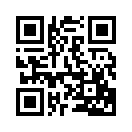2019年06月06日
オキナワシタキソウ(樹幹のてっぺんまでよじ登る生命力旺盛な藤本)
オキナワシタキソウ 〔ががいも科〕



オキナワキタキソウは林道脇の木のてっぺんまでよじ登る生命力旺盛な藤本。茎は他のものに絡みながら10m伸び巻きひげはない。葉は柔らかい洋紙質で卵状楕円形、長さ5~12cm、幅2~4cm、縁は全縁、葉先は尖って(鋭尖頭)、対生しています。葉の裏面には葉脈が突出していて、脈上には柔らかい毛が生えています。葉腋から2~3本の花柄をだし杯形の白色花を咲かせます。花冠は上部で5裂し反り返っています。果実は莢(さや)形、種子は扁平な狹卵形。oak
オキナワキタキソウは林道脇の木のてっぺんまでよじ登る生命力旺盛な藤本。茎は他のものに絡みながら10m伸び巻きひげはない。葉は柔らかい洋紙質で卵状楕円形、長さ5~12cm、幅2~4cm、縁は全縁、葉先は尖って(鋭尖頭)、対生しています。葉の裏面には葉脈が突出していて、脈上には柔らかい毛が生えています。葉腋から2~3本の花柄をだし杯形の白色花を咲かせます。花冠は上部で5裂し反り返っています。果実は莢(さや)形、種子は扁平な狹卵形。oak
2015年03月18日
ヤンバルセンニンソウ(3~5本の葉脈が目立ちます)

ヤンバルセンニンソウ きんぽうげ科
山地の林縁に生える常緑のつる性草本。茎は他のものに巻き付き3~5mに伸びます、葉は三出複葉で小葉は卵状長楕円形、葉先は尖り(短鋭尖頭)、全縁、表面には光沢があります。また3~5本の葉脈が目立ちます。花は白色で、腋生の円錐花序に多数つきます。Oak
2015年03月17日
ヤマヒハツ(薄緑色の小花を多く付けます)

ヤマヒハツ とうだいぐさ科
山地の林内や林縁に生える常緑の低木。枝は多数に分岐し高さ2~3mになります。葉は互生し、倒披針形、長さ5~10cm、幅2~4cm、縁は全縁、葉先はとがります。枝先や葉腋の総状花序に薄緑色の小花を多く付けます。雌雄異株。Oak
2015年03月16日
ネバリハコベ(茎頂の葉腋に小さい白い花)

ネバリハコベ(ヤンバルハコベ) なでしこ科
基部で多くに分岐して地を這う一年生草本。葉は心円形で対生し、長さ5~20mm、幅5~25mm、3~5本の葉脈が目立ちます。茎頂の葉腋に小さい白い花を咲かせます。五枚ある花弁は二つに深く裂けるので10本に見えるのはウシハコベの花に似ています。Oak
2015年03月14日
ヤブガラシ(五つの小葉からなる鳥足状複葉)

ヤブカラシ(ビンボウカズラ) ぶどう科
人里近くの原野や路傍、林縁に生える多年生のつる性草本。茎には短い軟毛が生え淡紫色、稜があり角張っていて、ところどころに葉と対生する巻きひげがあります。葉は五つの小葉からなる鳥足状複葉、葉縁には波状鋸歯がある。葉腋から出る長い集散花序に多くの緑色の花をつける。別名ビンボウカズラ。Oak
2015年03月13日
ヤンバルツルハッカ(輪散花序に白い小花を咲かす)

ヤンバルツルハッカ しそ科
原野や路傍に生える多年生草本、株全体に白色の柔毛が密生しています。茎は基部付近で分岐し、匍匐して20~60cmくらいに伸びます。葉は対生し、卵円形、長さ1~3cm、縁には3~5対の鈍い鋸歯があります。葉腋の輪散花序に2~8個の白い小花を咲かせます。Oak
2015年03月12日
アカバシュスラン(帯白色の小花を数個つけます)

アカバシュスラン らん科
山地の樹下に生える小形の地生ラン。草丈10~15cm、根元に数枚の葉をつけ、全体が赤紫色をしてます。葉は卵形で、長さ1.5~3cm,縁は全縁、葉先は尖ります。茎の先に5~7cmの総状花序を出し帯白色の小花を数個つけます。緑色で紡錘形の子房が印象的です。リュウキュウカイロラン(琉球かいろ蘭)、アカバカイロラン、アカバシュスラン等、図鑑によって呼び名が異なるがここでは「琉球植物誌(初島住彦著)」を採用した。Oak
2015年03月11日
サンキライ(山帰来)

サンキライ(山帰来) ゆり科
サンキライは別名猿捕(さるとり)茨(いばら)(サルトリイバラ)、カカラとも呼ばれます。山地に生える落葉するつる性の低木。地下茎には塊根(かいこん)がある。茎は硬く節ごとにジグザグに曲り、ところどころにトゲがあります。葉は卵状(たまごじょう)長楕円形(ちょうだえんけい)~卵(らん)円形(えんけい)、3~5の主脈がはっきり見え、葉先は鋭く尖る急鋭尖頭(きゅうえいせんとう)、脚部(きゃくぶ)には托(たく)葉(よう)が変形した一対の巻きひげがあります。1月頃葉腋の散形花序に多数の花をつけます。(上の写真のexif情報「撮影日時 : 2011/01/23 10:42:16」)。果実は球形で直径8~10mmで赤く熟します。Oak
2015年03月10日
ベニバナボロギク(橙色の頭花を下向きに咲かせます)

ベニバナボロギク きく科
休閑地や空き地に生えるアフリカ原産の一年生草本。茎は直立し、上部で多数に分岐し、緑色の縦線があります。葉は柔らかい膜質で互生し、上部は歯牙縁、下部は3~4対にやや深く裂け(中裂)ます(頭大羽裂)。若い葉は食べられ、もむとシュンギクに似たにおいがするようです。赤味を帯びた橙色の頭花を下向きに咲かせます。痩果には白色の冠毛があり、風によって散布される。Oak
2015年03月08日
ユウコクラン(葉には5主脈がはっきり見えます)

ユウコクラン らん科
ユウコクランは山地の常緑樹の樹下に生える多年生の地生ランです。偽茎(茎)は円柱形、5~15cm、直径5mm、二つか三つの節があり、各節は鞘状の鱗片に包まれている。鱗片は上部にいくに従い通常の葉に近い形になります。葉は茎の先端に2~3枚集まってつきます。葉には5主脈がはっきり見えます。10~35cmの花茎の先に総状花序をつけ、帯褐紫色の花を数多く(原色日本植物図鑑 北村四郎著)つけます。Oak
2015年03月07日
ヤンバルハグロソウ(葉は」全縁で濃い緑の暗緑色)

ヤンバルハグロソウ きつねのまご科
山地の路傍でよく見る多年生草本。茎には4稜があり四角形、下部は匍匐し節部から根をおろし、高さ30~60cmなる。葉は卵形で対生し、長さ3~8cm、幅2~4cm、葉先は鋭く尖る(鋭尖頭)、質は柔らかい膜質、全縁で濃い緑の暗緑色をしています。花は葉腋の穂状花序につけ、筒状花は上部で二つの唇形花弁に分かれ淡紅色、下唇弁の方がやや大きい。oak
2015年03月06日
ローゼリソウ(写真の調査待ち)

ローゼリソウ(ローゼル)
高さ1~2mになる1年生または多年生の低木。葉は深く三つにさけ互生する。この植物の一番の特徴は全体が暗赤色をしていることです。花は黄色、葉腋に一つずつつきます。花の下部、萼と苞は肥大して食用、薬用に利用するため栽培されています。Oak
写真の茎、葉、花の色がすべて暗赤色で普通にみる花は黄色、葉は緑で三深裂、萼と苞のみ暗赤色と違う気がする、下書き保存で調査待ち。
「沖縄園芸百科」(比嘉照夫他著)で農赤色系のリコとやや色の薄いビクター、緑色系アーチャーがあることが分かりましたので思い切って投稿することにしました。以下「沖縄園芸百科」の記述を引用しますので参考にして下さい。
「品種
ローゼルの品種は、食用と繊維用に大別されますが、現在では繊維用の栽培はほとんど行なわれていません。食用品種には次の三種がありますが、品種の改良はほとんど行なわれていないのが現状です。
●リコ(Rico)
一般に栽培されている濃赤色で、フエルト・リコ(PuertoRico)で発生した一変種で、収量も多く、ハワイ、フィリピン、台湾を経て沖純に導入されています。活花材料としても販売されますが、濃色すぎるきらいがあります。
●ビクター(Victor)
リコに比べると赤色がやや薄く、ピンクがかっており、直立性で早稲種です。収量はリコよりも劣りますが、活花材料としては秀れています。フロリダで選抜されジャマイカから広がった品種で、ジャマイカとも称されています。
●アーチャー(Archer)
緑色純で、西インド諸島のアンテグア島で見つかった変種です。町立性で、かっては広く栽培された記憶がありますが、ガク片が小さく収量も少ないため、現在では、見本程度に残っているにすぎません。」(沖縄園芸百科より)
2015年03月05日
ヤンバルミミズバイ(花冠を覆う長い雄しべが多数)

ヤンバルミミズバイ(ヒロハミミズバイ) はいのき科
山地に生える常緑の亜高木、高さ3~6mになり、一年枝には赤褐色の綿毛が生えています。葉は長楕円形~倒披針状長楕円形で長さ7~15cm、幅2~6cm、厚みがあり硬めの革質、葉先は尖り(鋭尖頭)、互生します。花は葉の落下した葉腋につき、直径8mmくらい、雌しべ1、花冠を覆うほどの長い雄しべが多数ついています。果実は卵状長楕円形、長さ1.2~1.5cm、黒紫色に熟します。Oak
2015年03月04日
ヤンバルミョウガ(林床に生える常緑の多年生草本)

ヤンバルミョウガ つゆくさ科
湿り気の多い林床に生える常緑の多年生草本。茎は高さ50~60cm、下部は倒伏し節部から根を下ろします。葉は長楕円状披針形で長さ15~20cm、葉先は尖り(鋭尖頭)、1cmくらいの葉柄部と葉鞘の鞘口(さやぐち)には淡褐色の毛(外向きにまっすぐにのびる開出毛)が生えています。花は葉腋の頭状花序に密につき、白色~淡黄緑色をしています。Oak
2015年03月03日
ユウレイラン(直径1cmくらいの白い花を咲かせます)

ユウレイラン らん科
森林の樹下に生える葉緑素を持たない腐生ランです。地上に5~6cmに伸びた花茎には、頂端に穂状花序、下方に2~3個の節があります。てっぺんの穂状花序には直径1cmくらいの白い花を咲かせます。各節には三角形の鱗葉(鱗片状の葉緑素を持たない葉)がつています。Oak
2015年03月02日
ヨルガオ(白色の大きな花で芳香を放ちます)

ヨルガオ ひるがお科
ヨルガオは熱帯アメリカ原産のつる性草本です。つるは5~6m伸び、垣根や他の植物によじ登り覆い尽くすほどの生命力旺盛な植物です。葉は心臓形、互生し、縁は全縁、葉先は尖ります。花はムーンフラワーと呼ばれ、日没から朝にかけて咲き、直径10~15cmの白色の大きな花で芳香を放ちます。Oak
2015年03月01日
リュウキュウイチゴ(花は白色、直径3~5cmくらい)

リュウキュウイチゴ ばら科
山地の路傍に生える低木。茎は斜上して2mくらいまで伸びます。葉は互生し、卵状長楕円形、長さ6~10cm、幅4~6cm、縁は歯牙状鋸歯があり、3浅裂しているのも見られます。裏面の中肋にトゲがあります。花は白色、直径3~5cmくらいで下向きにつき、果実は橙黄色で生食できます。Oak
2015年02月28日
リュウキュウコンテリギ(三分の一より上部に4~6個の鋸歯)

リュウキュウコンテリギ ゆきのした科
山地の樹下や林縁に生える1~1.5mになる常緑の低木。小枝はよく分岐し赤褐色を帯びています。葉は対生し倒卵状披針形、長さ1.5~5cm、幅0.7~2.5cm、三分の一より上部に4~6個の鋸歯があります。茎の先に小さな白い花を咲かせます。Oak
2015年02月27日
リュウキュウコザクラソウ(主脈や側脈が白い)

リュウキュウコザクラソウ さくらそう科
草全体が小さく5~10cmくらい、他の植物が高く生い茂るところではなく、人の手が加わる草原に生える一年草。葉は根本からロゼット状に生える根生葉で心形、長さ1~2cm、幅0.8~1.5cm、表面は毛が密生し、縁は鋸歯縁、主脈や側脈が白い。下部の中央から糸のような花茎を伸ばし、さらに上部で4~5本に分岐し、てっぺんに白い小花(径8mmくらい、中心は黄色)をつけます。Oak
2015年02月26日
リュウキュウテイカカズラ

リュウキュウテイカカズラ きょうちくとう科
リュウキュウテイカカズラは山地の林縁で見られる常緑の蔓植物。茎は長さ5mほどに伸び、他の植物によじ登り、あるいは垂れ下がる生育旺盛な植物です。葉は倒卵状楕円形で対生し、表面には照りがあります。5月ごろ、枝先や葉腋に円錐状の集散花序をつけ、黄白色の花を密に咲かせます。8月頃、細長いさやのような果実になり、裂開すると冠毛持った種子が出て風媒散布されます。Oak
2015年02月25日
リュウキュウトロロアオイ(花は黄色、径10cm内外)

リュウキュウトロロアオイ あおい科
栽培植物のオクラによく似たアオイ科の植物、茎は1~1.5mに伸び、株全体に粗毛があり、直立して分岐します。葉は長い柄があり、互生し、6~15cmの大きな葉は5~9枚に裂けています。各裂片の縁には鈍い鋸歯があります。花は黄色、基部は暗紫色、径10cm内外で葉腋につきます。果実は長楕円状卵形で長さ5~7cm、表面は粗毛で覆われています。Oak
2015年02月24日
リュウキュウナガエサカキ(葉腋に白い花をつけます)

リュウキュウナガエサカキ(シマサカキ) つばき科
リュウキュウナガエサカキは山地に生える高さ3~5mになる常緑の小高木。若い枝には伏毛あります。葉は細めの倒披針形で互生し、長さ5~8cm、幅1.5~2.5cm、葉先は鋭く尖る鋭尖頭、葉縁は全円、表面は無毛で濃緑色、裏面は絹毛がありいくぶん白っぽい緑色をしています。花は7月頃、葉腋に白い花を一個ずつ付けます。果実は液果、径1cmで黒く熟します。Oak
2015年02月23日
リュウキュウベンケイ(黄色い4弁花)

リュウキュウベンケイ ベンケイソウ科
リュウキュウベンケイは高さ30~120cmに伸びる多年生草本。葉は多肉質のへら状長楕円形で対生し、葉縁には鈍い鋸歯があります。茎の頂端の散房花序に黄色い4弁花を咲かせます。写真は西表島の集落内の路傍で撮りましたが栽培されたものが逸失したものと思われます。Oak

リュウキュウベンケイ ベンケイソウ科
リュウキュウベンケイは高さ30~120cmに伸びる多年生草本。葉は多肉質のへら状長楕円形で対生し、葉縁には鈍い鋸歯があります。茎の頂端の散房花序に黄色い4弁花を咲かせます。写真は西表島の集落内の路傍で撮りましたが栽培されたものが逸失したものと思われます。Oak
2015年02月22日
リュウキュウミヤマシキミ(香りのある、白い4弁花)

リュウキュウミヤマシキミ みかん科
林内に生える常緑の高さ1~1.5mになる低木。樹皮は灰色、若い枝は緑色、葉は互生し葉身は長さ6~13cm、幅1.5~5cm、倒卵状長楕円形、先はにぶく、基部はくさび形、葉縁は全縁、革質で光沢がある。5~10mmの葉柄は赤むらさき色を帯びる。雌雄異株で、雄花と雌花は別々の株に付く。香りのある、直径1cm位の白い4弁花を、枝先に多数付けます。果実は5~8mmで赤く熟します。Oak
2015年02月21日
リュウキュウモクセイ(淡黄白色で鐘形の花)

リュウキュウモクセイ もくせい科
高さ5~10mになる常緑の高木。葉は革質で硬め、対生し長楕円形、長さ5~12cm、幅2~4cm、刃先はとがり(鋭尖頭)表裏とも無毛です。6~7月ごろ葉腋に淡黄白色で鐘形の花を咲かせます。花は雌雄異株。果実は1~2cmの楕円形。11~12月に黒色に熟します。Oak
2015年02月20日
リュウキュウヨモギ(薬用として珍重)

リュウキュウヨモギ きく科
リュウキュウヨモギは方言でハママーチ(ハマ=浜・マーチ=松)と呼ばれるように砂葉や海岸の岩場にはえる多年生の草本です。茎は分岐が多く、下部は木質化し、5~60cmに伸びます。葉は松の葉によく似ている糸状の線形で幅0.5mm、2回羽状複葉です。円錐花序に球形の頭花を咲かせます。薬用として珍重されたが、乱獲が激しく、最近では自然の姿で見ることは出来なくなりました。Oak
2015年02月19日
マルバルリミノキ(葉の下面は黄褐色の毛が密生)

マルバルリミノキ アカネ科
林の中でよく見かける高さ1mくらいになる低木。枝は細く疎らに分枝し、全体に真っ直ぐに伸びる黄褐色の毛が密生しています。葉は柄がなく対生し、長さ7~10cm、幅3~4cm、葉先は鋭く尖る鋭尖頭、縁は全円です。又上面は無毛、下面は黄褐色の毛が密生しています。花は白色、肉眼でも毛が密生していることがわかります。果実は青色、径5mmくらい。Oak
写真の枚数が少なく、いい写真が撮れ次第差し替えます
2015年02月18日
ローズマリー(芳香とエッセンシャルオイル(精油)の木)

ローズマリー しそ科
地中海地方原産の常緑の薫りのある低木。幹は50cm~120cmにのび各節から多く分枝します。葉は各分枝した小枝の節に十字対生します。節間は下部で2~3mm、上部で10~15mm、対生する葉は長さ10~25mm、幅2~5mm、やや肉厚の針形葉です。上面は濃い緑色、下面は白っぽい毛が生え中軸(中肋)に反り返りっています。一見、外側の大きな一枚の葉と、内側の小さい二枚の葉と三輪生していると思ったのですが、内側の2枚は葉腋に出来た新しい枝の芽であることが分かりました。するとおびただしい数に分枝するはずですが、実際にはそうはなっていませんでした。光合成の盛んな外向きの枝芽は生長し、よく伸びていますが、内向きの枝芽は小さく生長が止まっていることが覗えました。この芽は木が生長し枝の木質化が進むに従って他の葉と同様消滅して行くものと思われます。春から夏にかけて咲く青紫色の花は葉腋に総状につきます。この植物の一番の特徴はその芳香とエッセンシャルオイル(精油)にあると思います。料理、薬用として用いられています。Oak
2015年02月17日
ワシントンヤシ(ビロウやシュロと同じ掌状複葉)

ワシントンヤシ やし科
ワシントンヤシはアメリカ南部からメキシコ北西部原産。ヤシ科は単子葉植物としては珍しく木本です。このワシントンヤシは高さ12~18mになる沖縄では一番高いヤシではないでしょうか。葉も他のヤシが羽状複葉に対し自生種ビロウやシュロと同じ掌状複葉です。耐寒性が強いと言われていますが冬場は葉先が痛々しいほど枯れています。花や実はまだ見つけていません。oak
2015年02月16日
ワニグチモダマ(長い花柄もつ花をぶら下げる)

ワニグチモダマ まめ科
ワニグチモダマは海岸林の内側に生える常緑の藤本です。つる状の幹(茎)は他の植物に絡まるように上に伸ばし、やがて先端は木の上から下向きに降り、沖縄では3月ごろ、長い花柄もつ花をぶら下げます。葉は三出複葉で、頂側葉は長楕円形、長さ12~15cm、他の小葉より葉柄が長い。淡緑色の花はやがて2~6個の豆果をつけます。豆果はやや大型で径8~14cm。海流に流されて分布するらしく砂浜に打ち上げられた豆果を見ることがあります。Oak